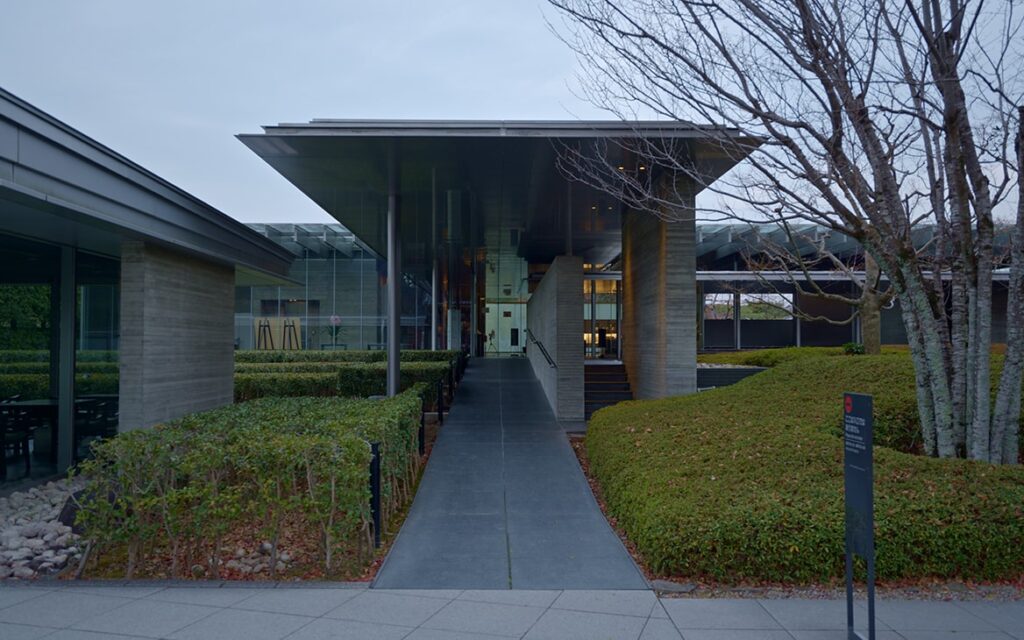観音堂は鎌倉時代初期(1185–1333)に元の本堂の跡地に建設されました。
しかし、その建築様式は、実際に建築された時代よりも500年も前の、古典的な天平時代(710–794)のものです。
この堂は、かつては本堂横の釣り殿として機能していました。
このシンプルな御堂が現存しているということは、特筆すべきことです。
平等院の長い歴史の中で、多くの宝物や御堂、塔が火災で失われ、初期の建造物で残ったのは鳳凰堂、観音堂、そして鐘楼のみでした。
観音堂は、鳳凰堂ほど古くはありませんが、他の木造建築物と同様に、何世紀にもわたって火災、戦争、地震、悪天候に耐えてきました。
観音堂の本尊は十一面観音立像で、かつて傍に安置されていた地蔵菩薩像は平等院のミュージアム鳳翔館で拝観することができます。
阿字池
密教で、宇宙万物は不生不滅という真理をあらわす文字として「阿」を用いて「大日如来」の世界にある宝池を模した庭園を現出させる。西方浄土への祈りを込めて造成される。池の中心には中島が置かれ、そこには阿弥陀仏の宮殿が建っていて、あたかも極楽の宝池に浮かぶ楼閣のように見えるとされる。
この言葉が使われている文化遺産
天平時代
729年から749年までの期間を指す。奈良の都平城京を中心にして華開いた貴族・仏教文化。この期間の文化を、聖武天皇のときの元号・天平を取って天平文化という。
この言葉が使われている文化遺産
寄木造
複数の木材を組み合わせて像の頭部や体幹部を造る木彫の技法。内部をくり抜いて重量を減らし、少ない木材で大きな像が造れるなどの利点がある。日本独自の技法で、平安時代中期から後期にかけて完成された
この言葉が使われている文化遺産
定朝
平安中期の仏師。父は康尚(こうじょう)。法成寺の造仏の功績により法橋の位を得た。現存するのは平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像のみ。仏像制作の上で寄木造の技法を完成させた。
この言葉が使われている文化遺産
浄土信仰
仏や菩薩が住む浄土世界に往生することを願う信仰。浄土には、阿弥陀仏の極楽浄土、薬師仏の瑠璃光浄土、弥勒菩薩の兜率天、観音菩薩の普陀落山などがある
この言葉が使われている文化遺産
西方極楽浄土
阿弥陀仏を教主とする浄土を指す言葉。人間界から十万億の仏土を隔てた西方の彼方にあり、蓮の花が咲き乱れ、煩悩のない安楽の世界とされる
この言葉が使われている文化遺産
藤原頼通
992(正暦3)~1074(承保1)、藤原道長を父に、源雅信(みなもとのまさのぶ)の娘倫子を母とする。後朱雀・後冷泉まで3代の天皇の関白を務める。1027(万寿4)、父道長の後受け宇治殿を引継ぎ、1052(永承7)に本堂を建立して平等院と号した。
この言葉が使われている文化遺産
平安時代
桓武天皇の平安遷都(794)から鎌倉幕府の成立(1185)まで約400年の間、政権の中心が平安京(京都)にあった時代。ふつう初・中・後の3期、すなわち律令制再興期・摂関期・院政期(末期は平氏政権期)に分ける。平安朝時代。
この言葉が使われている文化遺産